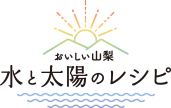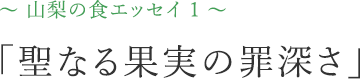山梨県出身の詩人・音楽家。大学卒業と同時に作詞家デビュー。
映画『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」の作詞で2001年度のレコード大賞金賞受賞。朗読ライブ、映画監督、脚本、翻訳など活動は多岐に渡る。
最新刊「はじまりはひとつのことば」(港の人)
八ヶ岳の伏流水と日本一の日照時間によってもたらされた、山梨県の豊かな食の幸。
県出身の詩人・音楽家である覚和歌子さんが綴る、とっておきの“食”エッセイ。
私のプライベートレーベルは「モモランチ」という。
桃をぱっかーんと割ったその真ん中に、桃太郎よろしくショートカットのセーラーガールが敬礼しているというレーベルマークは、おかげさまでたいへん評判がいい。(「ランチ」は昼食ではなく「船を進水する」「ロケットを打ち上げる」という意味launchの方。)
世の中でいちばん好きな食べ物はと聞かれれば、即座に「桃」と答える。
桃をいっぱいにしたプールで、心ゆくまで食べ泳ぎたい。それが夢だ。
小学生のころ、家は桃畑の真ん中にあって、通学路は桃畑の中の道だった。桜が終わると春のバトンを手渡すように桃の花が咲く。桜の色より鮮やかで濃い桃の花が満開の中を、友だちと駆け抜けて学校を目指した。夢みたいにきれいだ、と思ったことは強烈に覚えているけれど、当時あの春の通学路がどんなに奇跡的で恵まれていたことなのかは、大人になってからしみじみと知ったことだった。
夏は毎日学校のプールに通って真っ黒になった。
あのころ、夏の間一日でも桃を食べなかった日があっただろうか。家に着いて水着バッグを放り出して駆け寄るちゃぶ台には、いつも削ぎ切りにした桃が大皿にてんこ盛りにあった。友だちの誰かの家に上がりこんでも、母とお呼ばれに出かけても、行く先々で必ずふるまわれるのは大皿の桃だった。


子どもたちは桃をろくに味わいもせずに頬張った。続けざまに口に入れても桃はなくなることがなくて、お皿が空になる前にいつのまにか新しい皿がまた出てきた。したたる果汁とすべるのどごしは、夏の熱っぽい身体にとってうま味そのもので、ほとんど飲み込むようにして放り込むのに、飽かずいくらでも食べられた。それほど食べたらお腹をこわしてもよさそうなものだったが、果物に珍しく身体を冷やさない系質のせいか、身土不二のならいのせいか、山梨に生まれた子どもたちの身体はついぞ桃に負けることがなかった。そんな桃が購うものではなくて、隣近所や親戚からいただくもの以外ではなかったというのも考えてみればあり得ないことである。
若い青くさい桃も、子ども心にまた美味しかった。世間では熟してからの桃こそが「本来の桃」だと見なされている。そう知ったのは、東京の大学に入ってからだ。甘さの出ていない桃なんかを食べたらもったいないでしょ。そう言われて、もったいないことをそうとも知らずあたりまえにやっていたのだと思い知った。若い実のかたい歯ざわりと頼りない甘さを愛でる桃。どこからか到来して、いくら食べてもなくならない桃。お腹いっぱい食べる桃。それは産地だけに許される醍醐味と贅沢だ。


味わう間もなく夢中で頬張っていた昔に比べて、大人の物書きになった私は桃の何が自分を惹きつけるのかを、言語化できるようになってしまった。(それが良いのか悪いのかはわからない。)
桃の魅力は、楽園の罪深さと聖性のアンビバレンスである。アゴを使って噛むという手がたくも地道な行為なしに、舌で押せばつぶれる果肉の絶妙な硬度と、ほっておいてものどをすべり落ちてくれる怠惰な恍惚感。じゅる、というオノマトペが誘う蜜液の背徳的で豊潤なイメージ。
南国の果実のような強烈な主張がないからこその深い甘味が、ほんのりとかきたてる欲望のとめどなさといったら。(書きながら笑いがこみあげるのはなぜだ。) なぜこんなにも桃は多幸感が高いのか、いや高すぎるのか。
その一方、記紀神話ではイザナギノミコトが黄泉から逃げて帰ろうとする坂の途中、黄泉醜女(ゾンビ)を追い払うために投げたとあるように、桃は魔除けつまり浄化の象徴、聖なる果実として知られている。弱ったときにひとつ食べれば力が出ると言われるほど、その薬効は高いという。女の尻を思わせる丸みを帯びた、この上なく色っぽい形は、同時に社寺の装飾に見られる宝珠、業深い肉体を離れて透きとおる魂魄の形でもあるのだった。
桃から広がる想像力とおかまいなしの美味しさで、私は死ぬまで桃に寄り添われていたい。
プールで食べ泳ぎが叶わないのなら、せめて。